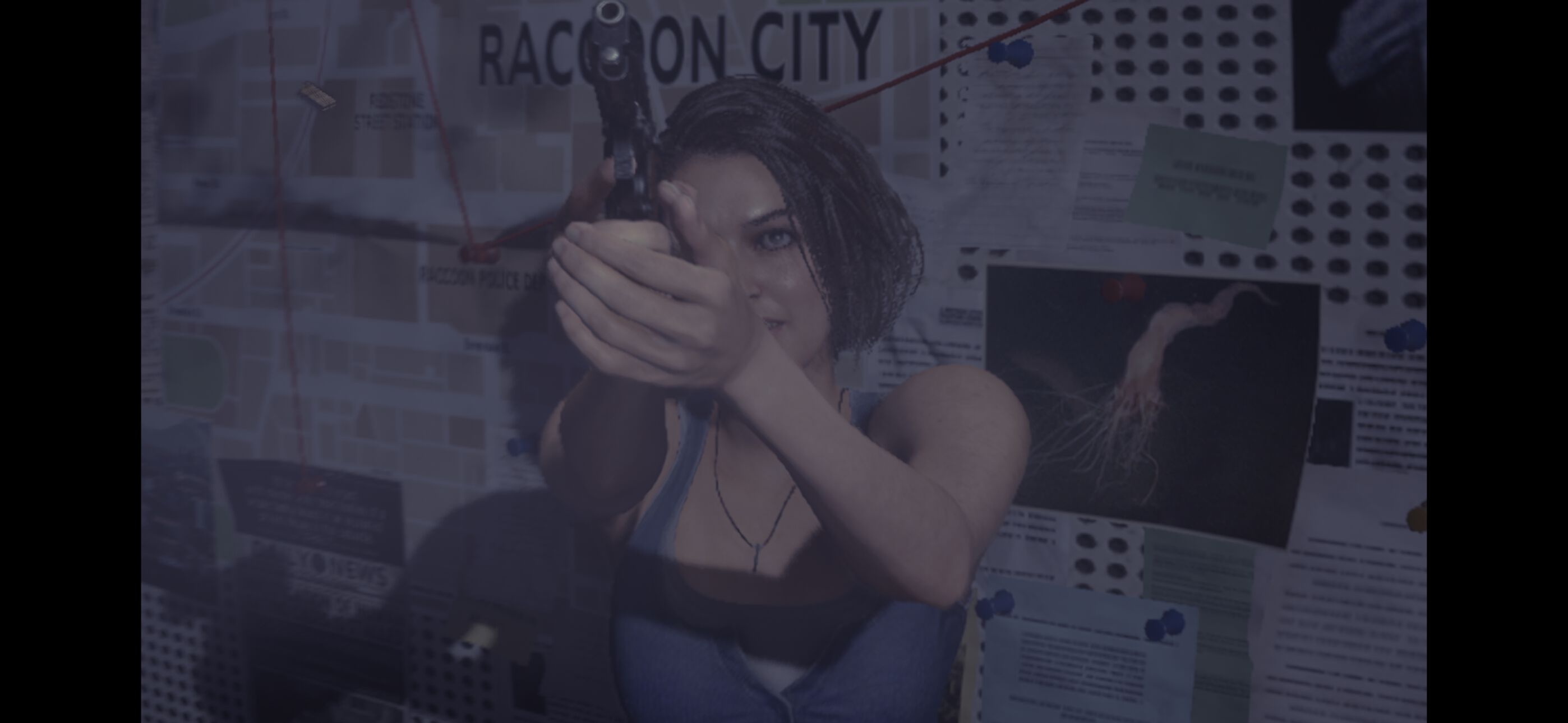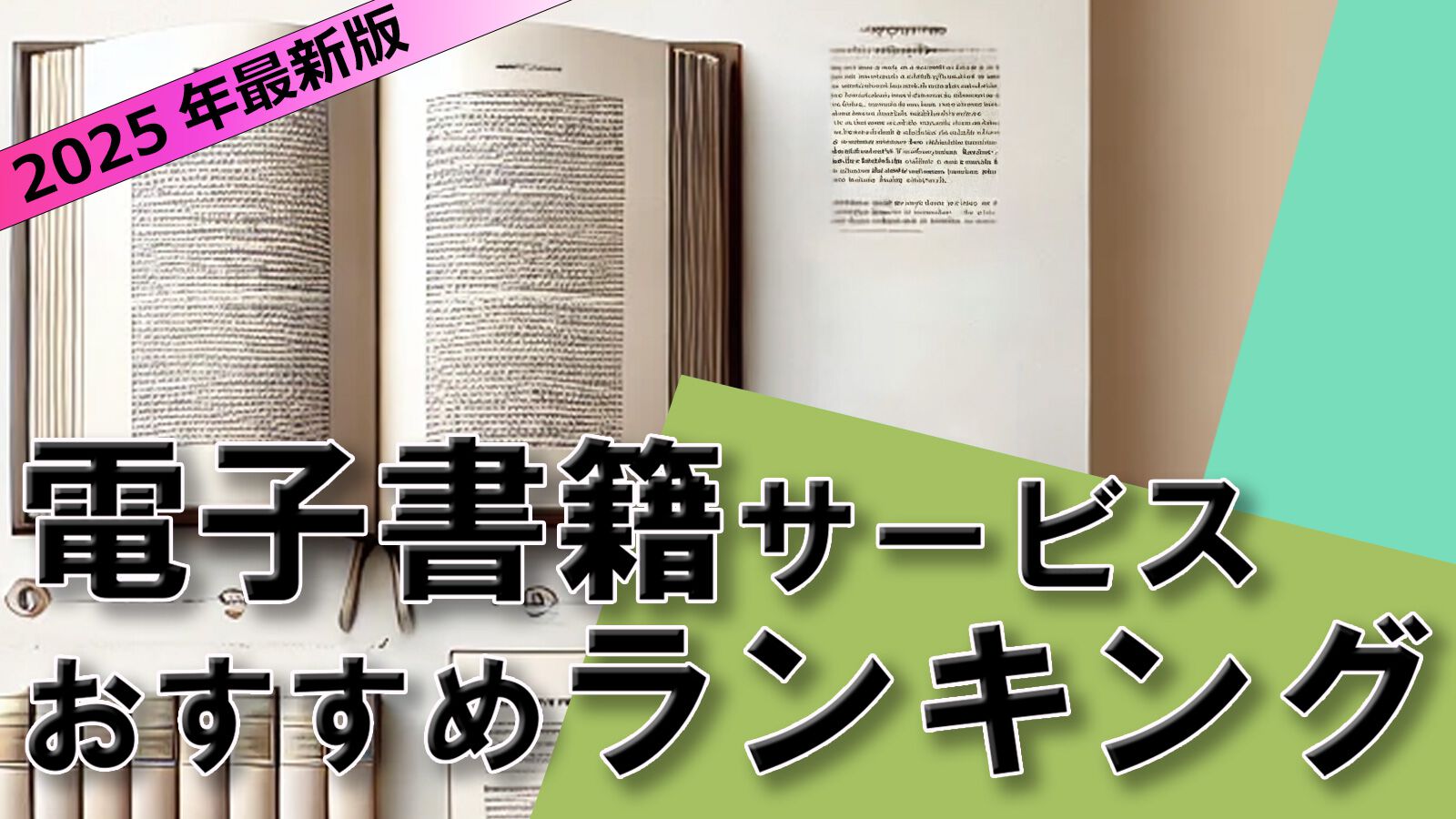金子一馬×画像生成AI×ローグライクの三身合体!
本作は『真・女神転生』シリーズのキャラクターデザインで知られる金子一馬氏がコンセプトプランナーとして参加。神や悪魔を使役しながらタワーマンションの最上階を目指していく、独自の世界観による物語が描かれる。
本作のもうひとつの特徴が、金子一馬氏の絵柄を学習した画像生成AIをゲームに組み込んだ“偽神オオカミ”システム。道中で遭遇する神=AIが、プレイヤーのそれまでの行動ログを参照し、新規カードをその場で生成。自分だけのカードが作れるという画期的なシステムだ。
生成されたカードは他のプレイヤーと見せ合うことができ、とくにプレイヤーに支持されたカードは金子一馬氏本人によってリファインされ、他のプレイヤーも使用できる形で実装されるという。
画像生成AIをゲームに組み込むという前代未聞の作品は、一体どのような経緯で生まれたのか? 本稿ではコンセプトプランナーの金子一馬氏、開発プロデューサーの齋藤 ケビン 雄輔氏の両名にインタビューを実施。ローグライクカードゲームと画像生成AIを融合させるに至った経緯や、AIを使ったゲーム作りの苦労についてお話を伺った。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/aa72a144d7ffd9ce74d58ef7f2d6ee3ab.jpg?x=767)
金子一馬(カネコカズマ)
『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズで生還設計やキャラクターデザインを担当。ソリッドで現代的な画風で神や悪魔といったモチーフを数多く手掛ける。2023年にコロプラに入社。『神魔狩りのツクヨミ』にてコンセプトプランナーを務める。
齋藤 ケビン 雄輔(さいとう けびん ゆうすけ)
コロプラ社所属。本作『神魔狩りのツクヨミ』開発プロデューサーを務める。
コンセプトデザインに迫る
たとえば本作には鳥居と目を掛け合わせた謎の結社っぽい意匠が出てきます。こうして説明するとすでに誰かがやっていそうなデザインですが、意外とやっていないものなので、そういった部分で他にない感じを出せればいいと思っています。
――今回はデッキ構築型のローグライクカードゲームにAIの要素を取り入れるという、個性の強い作品となっています。この方針が決まった経緯やきっかけをお聞かせください。
そこから「この世界観をベースに何を作ろう」という話になったのですが、やはり新しいものにしたいと。コロプラは新しいもの好きというか、それまでにないものをやりたいという気風が強い会社ですし。そこも踏まえて、システムにも新しいものを取り入れようとなり「やっぱりAIも入れたいよね」「じゃあローグライクのカードゲームにしよう」と決まっていきました。
そうした背景もあるため、デッキ構築型ローグライクとしては誰もが触りやすく遊びやすい形を目指して作ってきました。またその一方でローグライクユーザーの方にもご満足いただけるよう、いろいろな工夫も凝らしていますので、そこも楽しみにしていてください。
またAIという技術的に新しい挑戦もあるので、AIがゲームの体験にどう関わるのか、どう新しい体験が届けられるのかも大きな魅力になると思います。
――画像生成AIを利用すると決まった時期はいつごろですか? また、金子さんが画像生成AIと出会ったときの印象を教えてください。
世間では「怖い」とか「仕事を取られてしまうのではないか」という意見もありますが、個人的にはあまり恐怖心のようなものはなかったですね。
そしてAIとどう折り合いをつけていくか、どう付き合っていくかを考えていく中で「新しいゲーム体験としてお客さんに楽しんでもらえるチャンス」「チャレンジとしておもしろい」と思ったので、こうしてゲームの中に組み込むことになりました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/a6af9d8eeb487a2c7c3982c8063cdc48f.jpg?x=767)
画像生成AIを使う苦労
具体的な手法もご説明します。まず、金子さんが制作した素材をすべて学習させた状態で、何万枚、何十万枚と大量にイラストを生成させました。それを我々がひとつひとつ、人力で目を通して、学習素材に足るものをピックアップし、それを改めて学習素材として転用したのです。これを何度かくり返しながら、ゲームで使用する最終的なモデルを作っていきました。
――金子さんの絵にはパッと見でもわかる強い個性がありますが、それでも生成画像からの再学習ではどんどんズレていく可能性も出てくるかと思います。AI生成を利用して再学習させるにあたり、学習素材に使うか否かの選別はどういったレギュレーションを設けたのでしょうか?
あとはもう感覚的な要素になるのですが、「この絵が出たら面白いんじゃないか」という観点で選んだ素材もあれば、部分的に金子さんの個性を残していてうまく描けている素材も学習素材にしています。ここは選定する人のセンスに依る部分が大きかったです。
端的に言うと、イラストとして破綻しているものを除いてからは、選定する人の感覚、価値観で進めていったという感じですね。
――学習に悪影響を与える画像を機械的にフィルタリングした後は、人間の感覚を大事にされて学習を進めていったんですね。実際に学習されたAIから出力されたものを見て、いかがでしたか?
ただ、現時点ではそこから新しいインスピレーションを得るには至っていないのですが、「本当にこんなことしちゃうの?」という驚きはありましたね。
――学習量が少ない初期段階では、イラストとしてのクオリティが低いものも出力されていたのでしょうか?
それでも学習させたものとまったく違うものや、本当に絵にもならないノイズのようなものが出てくることは頻繁にありましたね。
その都度細かいパラメーターの調整を行いながら、ベストな学習方法や学習量を模索していきました。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/ad0eee2e02d721fb969e97a7ebbf4b0eb.jpg?x=767)
⇒コロプラ社が掲げるAIポリシーはこちら
慣れないAIに悪戦苦闘
たとえば本作ではプレイヤーのプレイログ、行動をもとにAIが生成したセリフが流れ、それから「あなたのカードはこれですよ」と画像を出すシステムになっているのですが、話す内容がうまく総括されなかったり、システムテキストをそのまま表示してしまったりといったこともありました。
また世界観に合わない言葉を喋ってしまうこともありましたね。本作ではゲーム内でカードのことを“神魔札”と呼称しているのですが、AIがそのまま“カード”と言ってしまうということがありましたね。こういった細かい調整はすごく多かったです。
――AIが固有名詞を使わず、カードと解釈したまま話してしまうのはおもしろいですね。
――世間一般ではAI利用による作業の効率化が期待されていますが、実際普通のゲーム開発と比較してみて、効率化できた事例はありますか?
レタッチを含めて考えると、やっぱり自分で描いた方が早いかなと思うこともありますから(笑)。
でもこうした模索を終えた先には、大きな効率化が果たせる部分が出てくる可能性はあります。そういう意味も含めて、今作はチャレンジ色の強い作品だと思っています。
実際に制作にかかる時間は大きく変わっていませんが、これもひとつの効率化なのかなと思います。
また物量を出したりそれを精査するところもAIが得意とする分野です。このようにAIの得意不得意をしっかりと理解して、人間とAIとで作業分担をしていけば、より効率的に進めていけると感じています。
――今作ではコーディングの分野にもAIが使用されているのでしょうか?
しかしコーディングの部分でAI支援が入ると、そういった時間も短縮できます。
――AIにコードを出力させるにあたって問題が起きたときに、それを解決するコツがあればお聞かせください。
コーディングでもイラストでも共通して、言葉でどう指示を出すかがすごく大事です。AIが理解しやすいようにこっちで翻訳して伝えてあげなきゃいけないというのは、コーディングでもイラストでも基本的に同じ考えかたですね。
たとえばイラストを生成したいときに、ただ単語を並べて出力指示を出しても画像生成がうまくいかないことは多々あります。とくに和テイストのイラスト出力は難しいですね。
――たしかに、プロンプト(AIに出す指示や命令文)で和のテイストを指示するのは難しそうですね。
この言語化能力に加え、“AIが把握できるプロンプトで指示できるかどうか”が、AIを使いこなす上でのポイントになると感じています。どんなものが出力されるかは人によってまったく変わってきます。
プロンプトによって、その人のそれまでにどのような人生を歩んできたかが出てくることもあるので、本当に面白いですね。
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/a7533b8cbe24707a038299f7c6582dbf2.jpg?x=767)
AIとゲームの未来像
私達は今作の開発・運営を通して、AIそのものはもちろん、使いかたもどんどんブラッシュアップしていけると考えています。
――本作はスマートフォンでもリリースされますが、AIまわりの処理はスマートフォンとサーバーのどちらで行われますか。
なので、端末のスペックや端末への負荷は気にしなくても大丈夫です。
――今回実際にAIを使ってみて、今後AIのここに期待したいと思ったところはありましたか?
いまはまだ完璧ではありませんが、じつはすでに理想に近いことはもうできるんですよね。ラフを描いたらそのまま仕上がります、みたいな。
また調べ物の際の情報収集をAIにお願いできないかも、試しています。情報収集に関しては、人がやるとどうしても時間がかかってしまいますが、AIはそれを効率よく、それも24時間対応できる可能性を秘めているので、今後に期待したいです。
このように、AIの活躍の場は今後どんどん増えてくのではないかと思います。
――AIにはハルシネーション(AIが事実と異なる情報を生成する現象)の問題もついて回ってくるかと思いますが、本作のAIでもハルシネーションは発生しましたか?
大事な決定を行うところで問題が起きてしまうと本来体験させたいものとズレてしまうので、AIの現状の特性を考えて、任せられる部分とそうでない部分を分けています。
――AI以外に本作で新しく挑戦したことはありますか?
またAIを含めたスモールチームでどれだけ早くタイトルを完成できるかを挑んでいる部分もあります。そのため、これまでとは違った開発体制、これまでの当社にはない作りかたをしています。AIを絡めたゲームをいち早く出すというチャレンジですね(笑)。
――スモールチームということですが、具体的にどれぐらいの規模なのでしょうか?
――なるほど、ものすごく小規模で作っているんですね。
AIを利用して少人数チームができれば、こうしたコミュニケーションの効率化もできそうですね。
なぜローグライクなのか
AIで一定のランダム性を持った出力ができると考えたときに、この特徴をうまく活かせるものとして挙がったのが、ランダム要素を活かせるローグライクだったんです。
実際ローグライクはインディーズを中心にコアな人たちが遊んでるゲームジャンルで、市場全体としてはけっこうニッチな存在だとは思っています。ただ今回はモバイルでもリリースしますし、金子さんのファンに向けたゲームでもあったので、なるべく間口を広げていろんな方に遊んでほしいと考えていました。
そのため山札や手札の数を少なくしたり、攻撃と防御を1ターンで全部行えるシステムを考え、なるべくテンポよく遊べるように仕上げています。
――ローグライクといえば入るたびにダンジョンの地形が変わるランダム性も特徴かと思いますが、マップの生成はAIになるのでしょうか? それともある程度パターンがあるのでしょうか?
「この要素は人の手でバランスを取った方がいいよね」とちょっとずつ引き算しながらたどり着いたAIの活用範囲が、現在の形ですね。
――そのほか、現在のバージョンにない部分でAI利用を試した要素があれば教えてください。
――おもしろそうですね!
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/a70b057108c6f7790405312cbdbe42db6.jpg?x=767)
AIと作る新たなゲーム体験に期待!
――生成AIイラストのほか、カード召喚時にはAI製テキストも出力されていました。金子さんの世界観を理解していないと難しいテキストに思えましたが、テキスト面でも金子さんの世界観を学習してるAIになるのでしょうか?
――プレイヤーが出力したカードの中からとくに人気が高かったものは金子さんと開発チームによるリファインのもと公式実装されるとのことですが、自分が生成したカードの人気が高かったかどうかは、ユーザー側からもわかるのでしょうか?
このように人気を集めるほど自分自身のカードが豪華になっていくので、そこで自分のカードへのリアクションは体験できるかなと思っています。
最終的に人気の高かったものからさらに我々運営がピックして公式化するわけですが、これをどうユーザーに伝えていくかは現在考えています。選ばれたカードだけでなく、候補に上がったものも見せられればと思います。
――最後に、アプリゲームを楽しんでいるユーザーへのメッセージを願いします。
今回はその望みが叶ったので、今までは腰を据えてロールプレイングゲームを楽しんでいたような方々も、毎日電車の中でもなんでもいいので、ぜひお手元で遊んでもらえるとうれしいです。
ただ遊んで終わりのゲームではなく、身近な人や周りの人に「私こういう絵のカードができたよ」「こんな展開でクリアできたよ」と話してもらえたら、そのやり取りも込みでAIを使ったゲーム体験が楽しめると考えています。
ぜひ気軽に触れていただいて、いろんな人とのコミュニケーションのきっかけになってくれたらうれしいですね。
撮影時のルックスについて
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu_app/35028/afaa3228eb15345fabba2523e53a90783.jpg?x=767)