
『Rez Infinite』の仕掛け人・水口哲也氏&SIE吉田修平氏が語るVRの未来
2016-12-22 13:25 投稿
『Rez Infinite』にちなんだ貴重な対談イベント
2016年12月21日、都内某所にて“Rez Infinite 米国 The Game Awards Best VR Game受賞記念対談”が開催された。
そこでは『Rez Infinite』を手掛けた水口哲也氏と、ソニー・インタラクティブ・エンタテインメント ワールドワイド・スタジオでプレジデントを務める吉田修平氏による対談が行われた。
 |
対談では、『Rez Infinite』の制作意図からVRという技術がもたらした変革、今後のビジョンなどが語られた。
ちなみに『Rez Infinite』とは、2001年にドリームキャストとプレイステーション2にリリースされた、シューティングゲームにリズムゲームの要素を加えた名作『Rez』のリマスター版。
しかしながら、ただリマスターをするだけではなく、プレイステーションVR(以下、PS VR)への対応や新たな要素も追加されている。
VRコンテンツとして世界中から高い評価を受けている本作。先日行われたThe Game Awards 2016では“Best VR Game Awards”を受賞し、PlayStation AwardsにおいてもPlayStation VR特別賞を受賞。そのほかさまざまなタイトルも受賞している。
PlayStation VR特別賞に選ばれた5本を遊んでみた感想
 |
 |
PS VR『Rez Infinite』がThe Game Awards 2016でBest VR Gameを受賞
本作をプレイしたことで得られる感情が、あまりに壮大で、膨大であることから「涙した」という声も少なくない。音と光の粒子が生み出す恐ろしく強い快感を語る人も多い。対談中にも、Oculus創業者であるパルマー・ラッキー氏が、本作をプレイして感動していたというエピソードも語られた。
その衝撃的な体験から、多くの支持を集めている本作。まさに『Rez Infinite』は、VR元年である2016年、もっとも多くの人の心に突き刺さったゲームなのだ。
VRによって広がった表現
そんなゲームとも芸術作品とも言える『Rez Infinite』を生み出した水口氏は、対談の最初に「26年間ゲームを作り続けてきたが、正直ここ5年間はつらかった」と語る。
その理由は、“クリエイティブで表現できる限界を感じた”ことにあるという。
当時『チャイルド オブ エデン』の開発を行っていた氏は、3Dと音楽が絡み付くことで生まれる、新しい感覚や体験に可能性を感じていた。だが「それはディスプレイという窓の向こう側の世界でしかない」と知り、限界を感じたからだという。
ちなみに水口氏は、かつてセガに所属していたクリエイター。水口氏は入社当時からVRコンテンツを扱いたかったとのことだが、水口氏がやりたいことを実現するテクノロジーが、当時はまだ存在していなかった。その結果、自身が理想とする表現を断念せざるを得なかったという。
こういった背景、経験を持つ水口氏は、近年VR技術のブレイクスルーが起きたことに端を発し、念願であったVRゲームの開発に着手。そこで初めて「これまで、自分はクリエイターとしてすごく我慢をしていた」と気づいたようだ。
「イメージが頭の中にある状態では、その世界に入り込むことができ、その世界を共感覚的に感じられます。しかしそれをゲームとして形にすると、その世界を画面という枠の中に押し込まなくてはいけません」とは水口氏の言。
だが水口氏は、そうしたクリエイティブにおける制約に否定的ではなく、「制約・制限がクリエイティブを進化させてきたという事実もあるので、これは否定するべきことではありません。ですが、あるとき自分はそこに限界を感じてしまったのです」と自身の経験から得られた答を述べた。
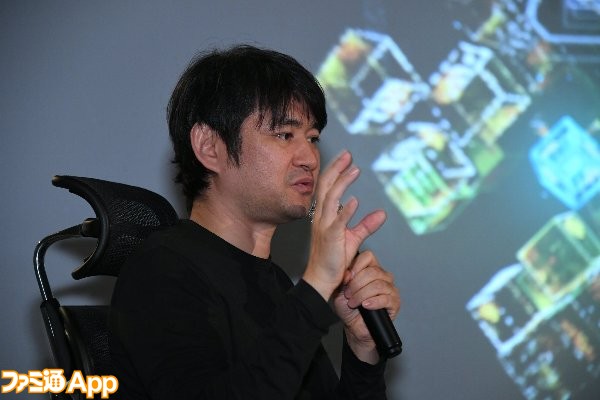 |
氏はこれまでのゲーム制作では、知らず知らずの間に自分を納得させ、自身の欲求を我慢させ続けていたと吐露した。
しかし、この制限は現在のVR技術によって一部開放され、表現の幅が広がった。そうして『Rez Infinite』のプロトタイプが誕生したのである。
水口氏がプロトタイプをプレイしたときには、自分が想像している世界に近づけたという感動のあまりに、涙が出たという。
水口氏の表現に関するこだわりの強さ、そしてそのこだわりの一片がVRという技術によって解放されたことが窺える。
『Rez Infinite』開発の陰に隠された努力
続けて話は『Rez Infinite』で追加された新モード“Area X”の開発秘話へ。
水口氏は『Rez』の開発コンセプトである“共感覚性”を表現するために、光の粒子・パーティクルをたくさん出すことを意識したという。
また「ピーターパンが空を飛ぶように、イルカが海を泳ぐように、立体の世界を自由に動き回る。自分が完全に自由であることを表現したかった」という思いもあり、パーティクルの存在はそれにも一役買っているという。
ターゲットオブジェクトを破壊することによって生まれるパーティクルが、VR世界で弾けたときの快感は、空間を自由に動き回っているという実感を表現するのに重要なファクター。
しかし、ただパーティクルを増やすことには意味がなく、そこには綿密に整えられたバランスが存在するようだ。
「パーティクルが弾けた瞬間は気持ちがいいけれど、粒子との距離があまりに近すぎるとVR酔いの気持ち悪さが勝ってしまう。かといって、遠すぎると気持ちよさがなくなります。それに、パーティクルが多すぎると処理落ちが発生してしまい、それも気持ち悪さにつながってしまいます」(水口氏)。
 |
そう語る水口氏は、細かなチューニングをくり返して、『Rez Infinite』で体験できる気持ちよさを作り上げた。
また、気持ち悪さ・VR酔い対策に関してはソニーのテックチームによる助力が大きかったことも語られた。具体的な話はされなかったが、テックチームから「これはやったらダメですよ」と注意された点を「とりあえず一度言われたようにやってみましょう」と改修してみたら、驚くほどよくなることが多かったのだという。
これに関して吉田氏は「ValveやOculus、さらにはソフトメーカーも、VR酔いなどに対する研究成果の情報共有は徹底しています。気持ちのよい体験を与えるには、一瞬たりとも気持ちが悪い瞬間があってはいけません」と応じ、気持ち悪さから生まれる“VRそのものへの否定的な感情”を防ぐための努力を明かしてくれた。
また水口氏は、『Rez Infinite』のコンセプトについても言及。『Rez』が”受胎”をテーマとしたのに対して、Area Xは”誕生”がテーマとなっており、それを彷彿とさせる表現がなされていることも裏話として語られた。
『Rez』は電脳空間の中にハッカーとして入り、ウイルスを駆逐するゲーム。だがその中に、精子の象徴ともとれるプレイヤーが、最終ボスとなる女性プログラム(=卵巣の象徴)にたどり着くという、生命の誕生の物語も隠されていた。そして“Area X”では、その先の”誕生”までのプロセスが暗喩として含まれているという。
作品を彩る音楽も、『Rez Infinite』の終盤ではウィルスを倒した際の音が、”誕生の祝祭”のように感じられるよう工夫も施されている。
水口氏は「“Area X”の最後には女性が誕生するのですが、このテーマを知ってプレイをするとウイルスを駆逐することで彼女の生誕に加担するような感覚も得られると思います」という気になるコメントを残している。
さらに水口氏からは、『Rez Infinite』のエンディングには分岐がある旨についても語られた。ふつうにプレイすると髪の長い女性が最後に出てくるのだが、どうやら一定条件を達成するとショートカットの女性が登場する模様。また最後にはパーティクルで構成された蝶が登場するが、こちらも分岐後は鳥になっているのだという。
それらの真相が気になる人は、プレイを通じてその壮大なテーマを感じ取ってみてはいかがだろうか?
VRゲーム制作現場はイキイキしてる!?
対談では、PS VRという開発環境、プレイ環境に関しての話も。
「正直なところ、このような表現技術が生まれるのはもっと先になると思っていました。何十万円ものお金をかけて機材を用意しなくとも、PS VRを使えばクリエイティブなものを共有できる。本当にありがたく思っています」(水口氏)
先述の内容からもわかる通り、水口氏がVR、とくにPS VRに寄せる思いは並々ならぬものがあるようだ。
また、このコメントに応じるように吉田氏は「どれだけいいハードを作っても、それを使いこなしていいコンテンツを作ってくれる人がいなければ、そのすごさは伝わりません」と、水口氏を始めとしたPS VRを支えるクリエイター陣への感謝を語っている。
 |
また、先に「ここ5年間はつらかった」と語る水口氏だが、現在のVR開発環境には満足をしている様子で「やればやるほどやってみたいことがどんどん出てくる。クリエイター人生の中で、いまがいちばん元気かもしれない(笑)」と笑顔を見せている。
ちなみに元気になっているのは水口氏本人のみではないようで、開発チームも活き活きとしているとのこと。
昨今のゲーム開発は、その規模がどんどん大きくなっており、ビジネスとしての難しさが表出してきている。失敗できないプレッシャーが大きくなりつつあるいま、実験的でもあるVRゲーム開発は小規模で行われており、ストレス抜きの楽しさを感じられる制作現場になっているという。
吉田氏によると、ソニーの一部チームは、「ああでもない、こうでもない」と楽しそうに議論を交わしながら、2週間に1本というハイペースでプロトタイプを上げているのだとか。「大きなタイトルは失敗できないというビジネス的な側面から、作業自体は淡々と進んでいくものが多いです。でも、VR開発チームはそれを尻目にうるさいほど賑わっての開発が進んでいます」とのこと。
また、このような雰囲気は初代プレイステーションがリリースされた当初に似ているらしく、「『クラッシュ・バンディクー』は10人くらいの小規模でワイワイと楽しみながら開発されていたし、あのころの楽しいゲーム制作が帰ってきたような気がする」と吉田氏が過去を振り返ると、水口氏も賛同。
水口氏は「僕たちも最初は12人くらいでの開発チームでした。何かを実現させようと、みんなで興奮しながら開発を進められました。これまで自分たちの中にスタックされていたエネルギーが放出されているような気さえします」と当時を振り返る。
生き生きした現場から生まれる生き生きしたコンテンツ。それらが市場を賑わせ、大きくしていくのだろう。今後のPS VRコンテンツには期待ができそうだ。
VRが生む壁も捉えかた次第
最後に語られたのは、VRの未来に関して。
「VRは経験を大きく変えるもの。これまでにあったものをすべて加速させ、人間そのものの可能性も広げていく」とは吉田氏の弁。水口氏はさらに加えて「VRだけではなく、複合的な技術が追加されていくと未来はもっと変わっていくでしょう」と語り、ここから両者がVRの明るい未来を見据えていることがわかる。
しかし一方で、この対談ではVRが生み出すであろう壁も示唆された。そのひとつがストーリーテリング、表現手法に関してだ。
これまで映画やドラマといったコンテンツは、カメラという第三者視点、つまりは監督が表現したい画角がそのまま視聴者に届けられていた。だがそれがVRになった瞬間に、どの画角を取るかはユーザーに委ねられるようになってしまう。
実際この変化を感じているクリエイターは多いようで、各所で課題として語られることが多い。
しかしこの課題を水口氏は「これまでのストーリーテリングを表現者が描いたひとつの線としてしか発信できなかったが、VRでは立体的に、有機的に表現、発信できるようになった」とポジティブに捉えている。
 |
VRは革命であり、130年続いてきた映像技術の進化のひとつ。古い考えに引きずられるのではなく、これから何が表現できるのか、どう表現していけばよいのかを学習していけばいいだけのことだという。
また、水口氏は「これからVRが当たり前という世界で育った人たちが作り上げていくコンテンツは、きっと私たちが作るものとは違うものでしょう。それを見るのも楽しみです」と語り、アフターVR世代のクリエイティビティにも関心を寄せていた。
これまで平面だった表現が立体へと移り変わるVR。そこに混乱を示す人もいれば、一方で可能性を感じる人もいる。映像表現のパラダイムシフトを迎えたとも言える本年の最後に、興味深い話を聞かせてくれた水口氏、吉田氏の両名。
彼らが作り出す今後のVRコンテンツに期待していきたい。
▼『Rez Infinite』の購入はコチラから!(※要SIEアカウント)
Rez Infinite ストアページ
▼いっしょに読みたい
PS VRで遊ぶために必要な物一覧
最新記事
この記事と同じカテゴリの最新記事一覧
【PS VR】言葉では伝えきれないもどかしさ……『ヘディング工場』はとにかくスゴイ!!
2017-02-08 22:34【PS VR】『デッド オア アライブ エクストリーム 3』でVRモードが1/24より解禁!! 製品版ユーザー対象の期間限定無料配布も
2017-01-23 20:50PS VR対応/専用ソフトが最大50%オフになる期間限定セールが1/26より開催!
2017-01-23 17:25PS4用YouTubeアプリがPS VRでの360度動画視聴に対応!
2017-01-20 13:17








